

コアネット教育総合研究所
放課後ラボ事業部 主任 佐々木梨絵
グローバル・シチズンシップ教育(GCED)とは、学習者が地球規模の課題に向き合い、地域・国際レベルでよりよい解決策を考え、積極的に行動することを通じて、公正・平和・寛容・包括的で持続可能な世界の実現を目指す教育のことです。
これは、UNESCOがSDGs(持続可能な開発目標)と連動して提唱したプログラムであり、特にゴール4「質の高い教育をみんなに」の中に「グローバル・シチズンシップを育む教育」が明記されています。
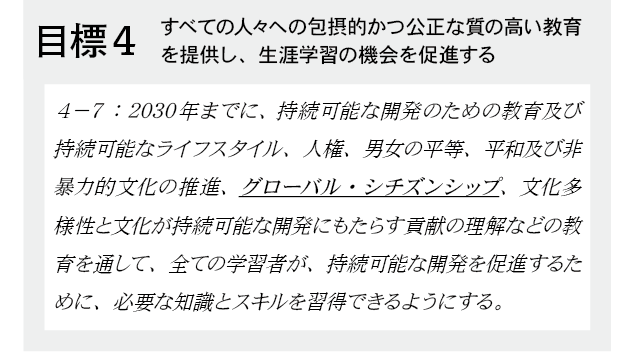
また、GCEDは、持続可能な開発のための教育(ESD)と密接に関係し、日本ではESDの一部として位置づけられています。UNESCOでは、2030年までに持続可能な社会の担い手を育成するために、この教育を戦略的事業の一つに掲げています。
そもそも、シチズンシップ(citizenship)とは、国籍や市民権という意味合いをもつ用語です。それらに「参加的な市民」という意味合いが加わったとされています。
シチズンシップ教育については、欧米諸国を中心に進められてきた教育であり、特に、イギリスにおいては、2002年の義務教育カリキュラムに組み込まれています。社会的・道徳的責任、コミュニティへの関与、政治的リテラシーの3つで構成され、後にアイデンティティと多様性がシチズンシップ教育には含まれることになりました。
つまり、シチズンシップ教育とは、「学習者が、参加型民主主義を理解・実践するために必要な知識・スキル・価値観を身につけ、行動的な市民となること」を目的としているものです。また、グローバル・シチズンシップのみならず、最近では、デジタル社会において、デジタル技術の利用を通じて、社会に積極的に関与し参加するデジタル・シチズンシップを育むこともUNESCO は提唱しています。
GCEDは、地球規模で「他者とともに生きる力」を育む教育であり、単なる国際理解ではなく、人権・多様性・連帯を基盤とした行動的学びを目指しています。
UNESCO(2015)の「Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives」では、GCEDの学びを三つの領域(認知/社会・情動的スキル/行動面)で整理しています。
グローバル・シチズンシップの概念や定義については、様々に存在してはいますが、グローバル・シチズンシップの育成に必要な資質である「当事者意識を持つ」「批判的思考と問題解決」「他者理解と他者協働」「行動する」といった点は、意見の差異はあっても一致している見解です。
GCEDは、「アイデンティティ教育の一形態」として位置づけることもできます。上記でご紹介したUNESCO(2015)が示す学習テーマにおいても、「異なるレベルのアイデンティティの理解」「多様なコミュニティのつながり」「違いと多様性の尊重」が記載されており、学習者が自他の多様性を認め、複合的なアイデンティティを形成していく過程を重んじられています。グローバル・シチズンシップを育む教育実践においては、この「多元的アイデンティティの育成」という要素は必要不可欠です。GCEDにおいては、国際理解を表面的な「異文化体験」にとどめるのではなく、他者との関わりの中で自らの価値観を問い直し、変容していくことが大切であると言えるでしょう。
【関連キーワード】
[参考資料・文献]